小学生が受ける代表的な資格試験である算数検定について
今回は10級の紹介をします
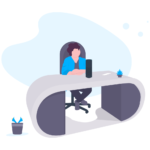
無学年式で学校のペースより早い
もしくはゆっくりな場合に
算数の勉強がどこまで出来ているか
客観的に確認するのにおすすめです
算数検定10級のレベル
算数検定は以下の級と学年の目安です
11級:小学校1年程度
10級:小学校2年程度
9級:小学校3年程度
8級:小学校4年程度
7級:小学校5年程度
6級:小学校6年程度
ここから5級以降は数学検定になり中学以降の
単元となります
小学校1年生や初めて検定を受けるお子様には
11級が良いかもしれません
初めての検定受験や11級については
以下の記事を参考にしてみてください
団体受験
通っている習い事で算数検定を団体受験できることを知らず
小1の2月に受験できるとのことでした
小1の12月に一般会場での試験で11級を受験したばかりでしたので
ちょっと期間が短いかなと思いましたが
本人も受けても良いというので試しに受けてみました
一般受験との比較はこんな感じです
・準備が楽
・合格証明書は変わらない
・会場がいつもの一般会場とは異なる
準備が楽
一般受験の場合、自分でネットから申し込みをして
会場を調べてといったことをする必要があります
地味に面倒くさいのが受験用の写真の用意
スマホで取ってアプリで証明写真用にサイズカットして
パソコンからUSBに移せば、コンビニで30円で
作れますがなんだかんだ30分くらいはかかります
これが紙一枚と検定費用を支払うだけで申し込みが
完了できるのは大きなメリットだと思います
合格証明書は変わらない
11級は一般会場で受験、10級は団体受験会場で受験しましたが
合格証明書は変わりませんでした
11級や10級では何か提出するということは
少ないような気もしますがどちらも同じフォーマットで
発行されており、一般か団体かで差異はないようでした
会場が一般会場とは異なる
一般会場の場合、基本的に知り合いや習い事の先生は
おらず、知らない大人や知らない子供に交じって
受験することになります
他の級も同じ部屋で受けることも多いため
どんな子供が受けているのか様子が分かります
団体受験の場合はその反対で、同じ習い事に行っている子供と
知っている先生が居て、会場についてもいつもの習い事と同じ
場合もあると思います
慣れた環境なので緊張等はしにくいかと思いますが
検定の雰囲気に慣れたい、というような目的がある方は
向かないかと思います
算数検定10級の内容と取り組み方
内容としては足し算、引き算に加えて
初めて掛け算が出てきます
とはいえ、うちの子が受験するときには
九九は全く覚えないまま受験させました
但し、掛け算が出ることは過去問を見たときから
分かっていたので、九九の代わりに掛け算の意味だけ
教えておきました
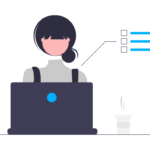
3x4であれば、
3+3+3+3
という意味だよ
意図としては、いきなり九九の暗記から入ってしまうと
その後算数=暗記となってしまい、後伸びしない懸念が
あったため、無理に九九は覚えずに、まずは掛け算の意味
から入ってみようと考えました
図のひろさ比べの問題と算数検定特有の問題で
間違いがありましたが合格とはなりました
算数検定10級のまとめと感想
算数検定10級については、効果測定というより
合格証を貰ってうれしい!という成功体験が
メインだと思います
小学校という成長著しい過程で受験から
結果が分かるまでが1か月程度掛かるので
どうしても学習計画を立てたりフィードバックには
向かないと考えています
特に検定の受験当日は問題も持ち帰り不可なので
子どもに受験の感想を聞くくらいしかできません
とはいえ定期的に受けて、学習した範囲に穴が空いていないか
受験環境に慣れているか、等を調べるには良いと思います

9級は九九を覚えていないと解くのが難しそうなので
まずは九九を覚えて少し筆算の練習もしてから
受験しようと思います
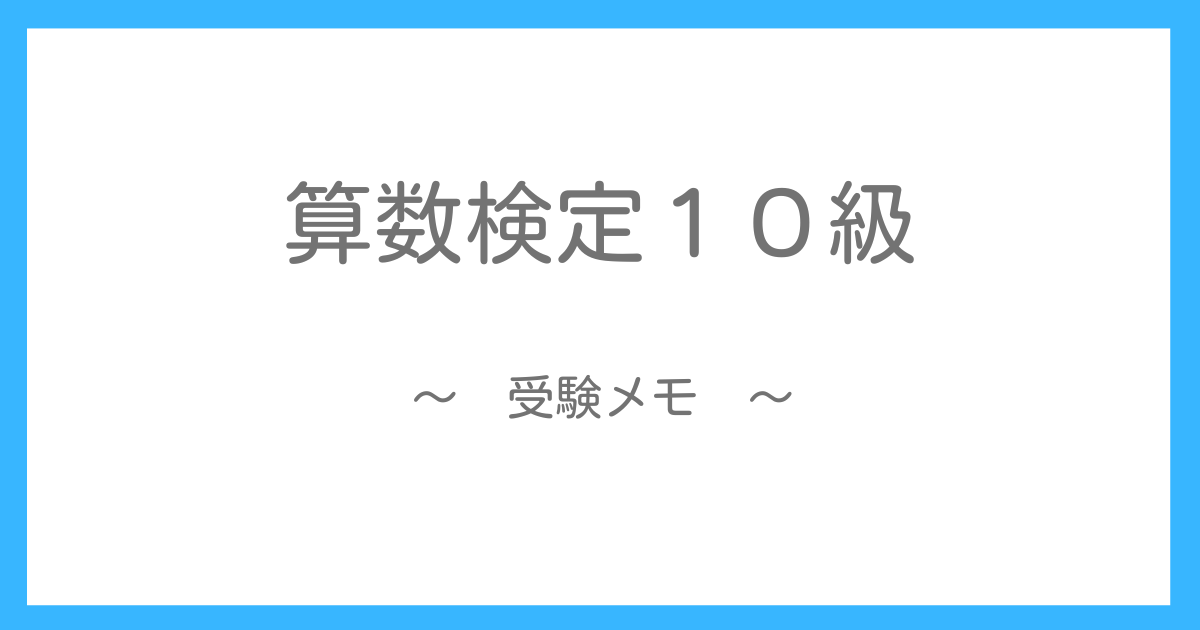
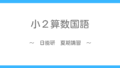
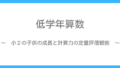
コメント